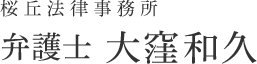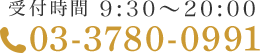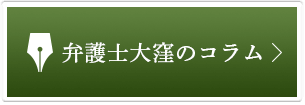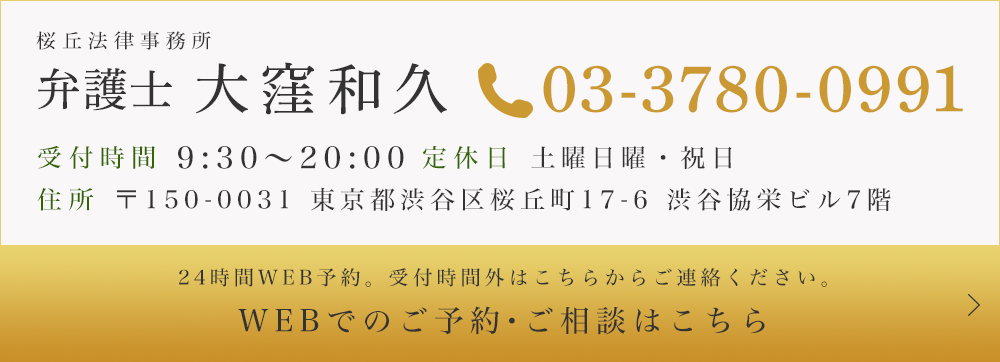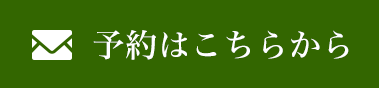最近、インターネット上でのなりすまし行為についての相談を多く受け付けております。
インターネット上でのなりすまし行為とは、本人の実名や本人がインターネット上で使っているハンドルネームをつかったり、本人の写っている画像を使ったりしてあたかも本人がそのアカウントを使っているような形でインターネットの掲示板やSNSで投稿を行うことを指します。
インターネット上でのなりすまし行為が続いて本人であれば絶対に投稿しないような内容が投稿されネット上に拡散された結果、本人の名誉が毀損され続けるということも珍しくありません。またインターネット上のなりすまし行為による被害は有名人ばかりではなく、一般の方でも多いのが実情です。本人の知り合いが嫌がらせでインターネット上のなりすまし行為を行うということも少なくありません。
インターネット上のなりすまし行為は、どうせ自分がやっていることがばれることはないだろうという安易な気持ちで行っている人が多いようです。確かになりすまして投稿する際には、どこかに自分の実名や住所を入力するわけではありませんので、自分がやっていることが特定されるわけはないだろうと考えるのでしょう。
しかしながら実際には裁判上の手続を使いインターネット上でのなりすまし行為をした者を特定することは可能です。特定するためにはまず投稿がなされたサイトやSNSを運営する会社に対して仮処分を申立て、投稿者の発信者情報(ログイン時のIPアドレス)の開示を求めます。開示された投稿者の発信者情報からは投稿者が利用しているプロバイダが特定できます。そのプロバイダの運営会社に対して発信者情報開示請求訴訟を提起して判決を得れば投稿者の情報(氏名、住所、メールアドレスなど)が判明し、投稿者の特定に至ります。
インターネット上でのなりすまし行為により本人の名誉が毀損されている場合には、加害者に対しては損害賠償請求を行うことが可能です。それでは具体的にどの程度の損害賠償が得られるのでしょうか。損害賠償の金額は事案の内容によりますが、近時判例タイムズで紹介された裁判例(大阪地裁平成29年8月30日判決 判例タイムズ1445号202頁)の事案が参考になるかと思いますのでご紹介いたします。
この事案では、加害者はSNSで被害者のなりすましアカウント(被害者がSNSで使っていたアカウント名と同じ名前を使い、かつ被害者の顔写真を使用したもの)をSNSで作りました。このなりすましアカウントは約一か月程度SNS上にそのままの状態で存在していました。そして加害者はこのなりすましアカウントを使って、他者に対し「ザコなんですか」「お前の性格の醜さは、みなが知った事だろう」などといった誹謗中傷を繰り返したり、被害者の顔について醜い顔である旨の侮辱行為を行っていました。そこで被害者は加害者を特定した上で、損害賠償請求訴訟を裁判所に提起したのです。
裁判所はこの加害者のなりすまし行為によって、被害者の名誉権及び肖像権が侵害されたとして、加害者に対し慰謝料60万円の支払を命じました。
しかし裁判所が認めた損害はこの慰謝料だけではありません。被害者は加害者を特定するために、SNSの運営会社に対する仮処分およびプロバイダに対する発信者情報開示訴訟を行いましたが、その為に58万6000円の弁護士費用を負担しました。この弁護士費用についても損害として加害者に対して支払を命じているのです。
さらに裁判所はこの損害賠償請求訴訟自体の弁護士費用(12万円)も損害として加害者に対して支払を命じておりますので、合計130万6000円の損害賠償責任を加害者は負うこととなったのです。
安直な気持ちで行ったなりすまし行為であっても、その結果上記のように大きな代償を払うことになることは良く知っておくべきだと思います。
また一方で、なりすまし行為がどこの誰によって行われたか分からないと言って泣き寝入りする人も多いですが、法的手続をしっかりとっていけば上記のような形で判決を得た上で被害回復へ繋げることもできますので、被害にあったら弁護士に相談されることをお勧めいたします。