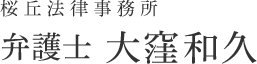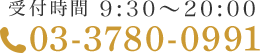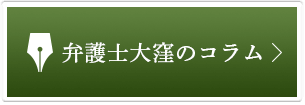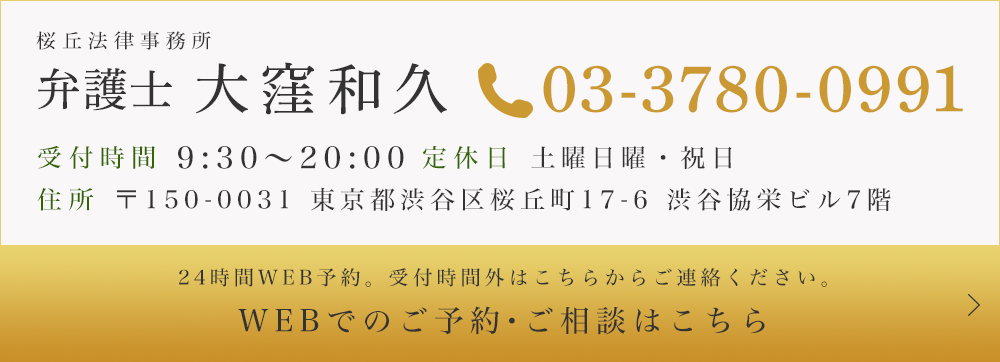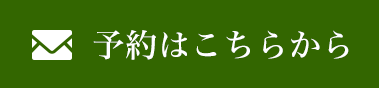グーグルマップの口コミの投稿において名誉毀損がなされることは良くありますが、その場合でも、投稿者の発信者情報開示についてグーグル社が任意で応じることはなく、裁判手続でも積極的に争ってくるのが通常です。
発信者情報開示の訴訟について、ハードルになっているのは「侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき」(権利侵害の明白性)という要件です。この要件は、投稿によって請求者の名誉毀損がなされたことだけではなく、「違法性阻却事由の存在をうかがわせるような事情の存在しない」ことまで必要とされており、開示を求める側がそれを立証しなければなりません。この立証が出来ないことを理由として発信者情報開示を断念するというケースは多々あります。
ただ、この権利侵害の明白性について、開示請求側に不可能なことまで証明を求めるようなことになっては制度趣旨を没却することになるとして、一審の原判決内容を覆した東京高裁の判例が出ましたので、本ブログでも簡単に取り上げたいと思います。
事案としては、グーグルマップの口コミで、”営業の電話がしつこいです。特定商取引法の17条で勧誘を断った消費者への再勧誘は禁止されているのに何度も掛かってきます”などといった投稿をなされた会社が、グーグル社に対して発信者情報開示を求めたものです。投稿をなされた会社は、顧客と電話禁止対象者を一元管理しており、勧誘を断った人については電話禁止対象者に加える仕組みをとっているので、勧誘を断った消費者への再勧誘はありえないと主張しました。
この点について、東京地裁の原判決(令和元年(ワ)14308号)は、「原告が主張する仕組みがとられていたとしても,テレフォンアポインターから本社管理部門に正しく電話禁止対象者の報告がされていなかったり,記載漏れ等により契約者リストに電話禁止対象者が正しく記載されていなかったり,テレフォンアポインターが誤って自ら担当する電話帳から電話禁止対象者を正しく消していなかったりすることにより,本来電話勧誘を行うべきでない者に電話勧誘がおこなわれてしまうおそれがあることは否定し難い」として、人為ミスによる再勧誘の抽象的な可能性があることを理由として、権利侵害の明白性要件を否定し、開示を認めませんでした。ただ、人為ミスが全くないことまで立証することは困難を極めるものであり、この判決のロジックですと発信者情報の開示が認められることはほぼ無いと思われます。
これに対して、東京高裁の控訴審判決(令和2年(ネ)1959号)は、人為ミスによる再勧誘の可能性があること自体は認めましたが、「被害者である控訴人におよそ再度の電話勧誘をすることはなかったという不可能に近い立証まで強いることは相当でない。その意味で、プロバイダ法4条1項で定める「権利侵害が明らか」という要件について、権利侵害された被害者が発信者に対して損害賠償請求をする訴訟における違法性阻却事由の判断と完全に重なるものではないと解され、再勧誘の可能性が全くないことまで請求原因として立証することを要しないというべきである」として、原判決の判断を覆して権利侵害の明白性要件を肯定しました。
本事案については上告されており、最終的な判断はまだなされていないようですが、グーグルマップの口コミに関して発信者情報開示を事実上封じかねない一審の判決はバランスを欠くと思われますので、本高裁控訴審判決の様な判断が定着することを期待致します。