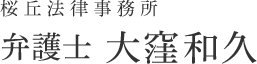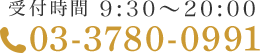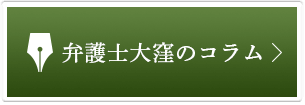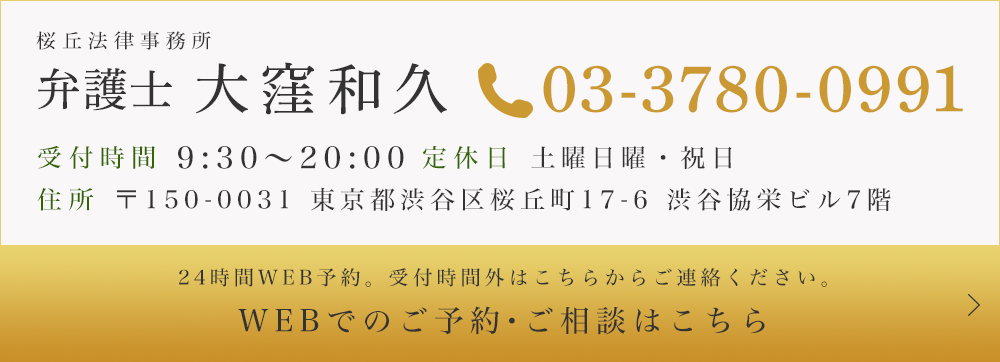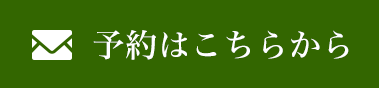インターネット上に一度掲載された情報が、いつまでも残り続けることに不安を感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。特に、過去の不名誉な情報が検索結果に表示され続けることは、社会生活を送る上で大きな負担となり得ます。
今回は、時間の経過などを理由として過去のブログ記事の削除が認められた裁判例(名古屋地方裁判所 令和6年8月8日判決)について、解説します。
1 はじめに
この判決は、記事が掲載された当初は問題がなかったとしても、時間の経過によって記事を掲載し続けることの正当性が失われる場合があることを示した点に特色があります。名誉毀損と表現の自由、そして「忘れられる権利」にも関連する論点を含んでいます。
2 事案の概要
あるブログサービス上に、原告が過去に代表取締役を務めていた会社(以下「本件会社」)に関する記事(以下「本件記事」)が掲載されました。 本件記事は、「本件会社が詐欺のように元本保証と高配当により資金調達を行っていたが突然閉鎖したようであり、計画的な倒産の可能性がある」といった内容でした。つまり、本件会社が詐欺的な行為をしていた可能性を示唆するものでした。本件記事が書かれるきっかけとなった新聞報道があり、本件記事掲載後、原告は本件会社の業務に関して出資法違反で有罪判決を受けています。
原告は、「この記事は名誉棄損であり、プライバシーも侵害している」と主張し、ブログ運営者である被告に対し、記事の削除を求めて裁判を起こしました。
3 争点
この裁判の主な争点は、「本件記事が原告の名誉権を侵害するかどうか」、特に「時間の経過によって、本件記事を掲載し続けることが法的に許されるのかどうか」という点でした。
原告は、「記事が掲載されてから10年以上が経過しており、もはやこの記事を公衆の目に触れさせ続ける公共の利益はほとんどない。記事の公共性は失われている」と主張しました。
被告は、「記事の内容は、原告が有罪判決を受けた事実などから真実であり、会社の信用性に関する情報として引き続き重要だ。公共性も公益目的も認められるため、公正な論評として保護されるべきだ」と反論しました。
4 裁判所の判断
裁判所は、以下の点を考慮し、原告の請求を認めて記事の削除を命じました。
(1)名誉毀損の成立
まず、本件記事が「詐欺のような」「詐欺の可能性が高い」といった表現を用いていることから、原告の社会的評価を低下させるものであると認定しました。
(2) 本件記事の前提事実が公共の利害に関する事項にあたらない
裁判所は、名誉毀損にあたる表現の差止めは、表現の自由との関係で慎重に判断する必要があるとしつつ、意見や論評の差止めが許される場合を限定的に示しました。具体的には、その意見や論評が公正な論評に当たらないことが明白であり(公共の利害に関するものでない、公益目的でない、前提事実が真実でない、人身攻撃に及んでいるなど)、かつ被害者が重大で著しく回復困難な損害を被るおそれがある場合に限られるとしました。
裁判所は、本件記事が掲載された当初は、前提となる事実に真実性があり、公共性や公益目的も認められ、公正な論評に当たるものであったと判断しました。
しかし、以下の事情から、時間の経過とともに状況が変化したと指摘しました。
・有罪判決の言い渡しから9年半以上、記事掲載からも11年以上が経過していること。
・有罪判決の執行猶予期間は既に満了し、刑の言渡しは効力を失っていること。
・記事で引用されていた元の新聞記事も、インターネット上で一般的に閲覧できなくなっていること。
・本件会社や原告に関する刑事手続きが終了した後も、長期間にわたって閲覧され続けることを想定して投稿されたとは認め難いこと。
・本件会社の行為が、記事掲載後も継続的に社会の関心事となっているような事情は見当たらないこと。
これらの点を総合的に考慮し、裁判所は、本件記事が前提とする事実は、口頭弁論終結日(裁判の最終段階)の時点においては、もはや公共の利害に関する事項に当たるとはいえないことが明白であると判断しました。
5 結論
以上のことから、裁判所は、本件記事の掲載を続けることによって原告が著しく回復困難な損害を被るおそれがあると認め、被告に対し、本件記事の削除を命じる判決を下しました。
6 本判決の意義
この判決は、インターネット上に掲載された過去の記事による名誉毀損について、「時間の経過」という要素が、記事の公共性を判断する上で極めて重要になることを明確に示した点で大きな意義があります。
たとえ掲載当時は真実であり公共性があったとしても、時が経つにつれてその情報が社会的な関心を失い、個人の名誉やプライバシーを不当に害し続ける場合には、記事の削除が認められる可能性があることを示唆しています。
インターネット上の情報は半永久的に残り、拡散する可能性があります。 このような特性を踏まえ、過去の情報による権利侵害と表現の自由のバランスをどのように取るべきか、改めて考えるきっかけとなる重要な判例といえるでしょう。