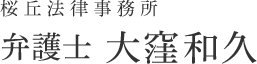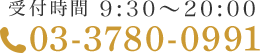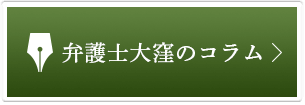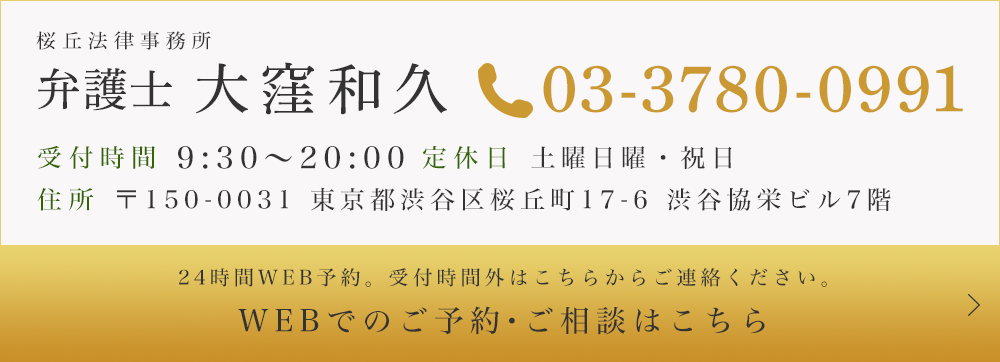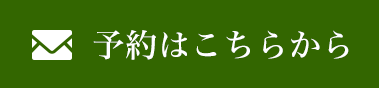企業・組織の不正行為が後を絶たない現代において、組織内部からの「公益通報」は、社会の健全性を保つ上で極めて重要です。しかし、通報者が不利益な取扱いを受ける事例が多発し、通報をためらう大きな要因となっていました。
このような状況を改善すべく、「公益通報者保護法の一部を改正する法律」が今年の6月11日に施行されました。この改正は、公益通報を理由とする不利益な取扱いを強力に抑止し、もし通報者が被害を受けた場合には、これまで以上に手厚く救済することを目指すものです。
・なぜ、今、法改正が必要とされたのか?
これまでの公益通報者保護法にも通報者保護の規定はありましたが、実運用上の課題が指摘されていました。特に、通報者が不利益な取扱いを受けた場合でも、それが「公益通報を理由とするもの」であることを通報者自身が証明する負担が非常に大きく、結果的に救済が困難となるケースが多く見られました。また、保護の対象となる通報者の範囲が限定的であることや、事業者側の内部通報体制が不十分であったり、通報自体を妨げる行為があったりすることも問題視されていました。
今回の法改正は、これらの根本的な課題に対処し、通報者への不利益な取扱いを徹底的に排除し、通報者が安心して声を上げられる環境を整備することに、その趣旨があります。
・改正によって何がどう変わるのか?
今回の法改正は、公益通報者保護の「抑止」と「救済」を大きく強化する画期的な内容を含んでいます。
1. 保護される通報者の範囲が拡大されました これまでの労働者に加え、事業者と業務委託関係にあるフリーランスの方々も、新たに保護の対象となる公益通報者に加わりました。これにより、多様な働き方をする方々も、安心して不正を指摘できるようになります。
2. 不利益な取扱いに対する「推定規定」が導入されました 公益通報をした後に解雇や特定の懲戒処分が通報の日から1年以内に行われた場合、「公益通報を理由として行われたもの」と推定されることになりました。これは民事訴訟において、通報者側が「通報が理由だ」と証明する負担が大幅に軽減され、事業者側が「通報が理由ではない」ことを証明しなければならなくなるため、通報者の「救済」が格段に容易になります。
3. 不利益な取扱いに対する「直罰規定」が新設されました 公益通報を理由として解雇や懲戒を行った者に対し、6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科されることになりました。また、法人に対しては3,000万円以下の罰金が科される可能性もあります。これにより、通報者への報復行為に対する強力な「抑止力」が働くことが期待されます。
4. 通報妨害行為や通報者探索行為が禁止され、違反行為は無効となります 事業者が、正当な理由なく「通報しない」合意を求めたり、通報した場合に不利益な取扱いをすると告げたりする行為が明確に禁止され、そのような合意は無効とされます。また、正当な理由なく通報者を特定しようとする行為も禁止されます。これらは通報への「抑止」要因を取り除くための重要な措置です。
5. 事業者への体制整備義務が強化され、行政による監督も強化されました 常時使用する従業員が300人を超える事業者には、社内の公益通報対応体制を整備し、従業員に周知する義務が明確化されました。これに違反した場合、内閣総理大臣による助言・指導に加え、勧告、そして従わない場合の「命令」が可能となり、命令に違反すれば刑事罰(30万円以下の罰金)や公表の対象となります。さらに、内閣総理大臣には事業者への報告徴収や立入検査の権限も新設されました。これにより、内部通報制度の形骸化を防ぎ、実効性のある体制整備を強力に促す「抑止」効果が期待されます。
・期待される効果と実務上の影響
今回の公益通報者保護法改正は、通報者への「抑止」と「救済」を大幅に強化するものです。
特に、不利益な取扱いに対する「推定規定」や「直罰規定」の導入は、通報者が安心して声を上げられる心理的な安全性をもたらし、もし被害を受けたとしても、法的手段によって救済される可能性が高まります。弁護士の立場から見ても、不利益な取扱いを受けた場合の損害賠償請求や解雇無効の訴訟において、通報者側の立証負担が軽減されることは、通報者にとって極めて有利な解決に繋がる大きな変化です。
事業者にとっては、内部通報制度の適切な運用が、単なる努力義務ではなく、刑事罰を含む法的リスクを回避するための必須事項となりました。これにより、各企業で内部通報制度の質が向上し、組織全体のガバナンス強化と健全化が進むことが期待されます。