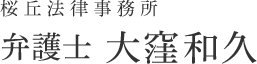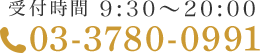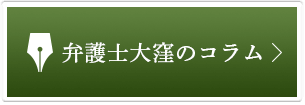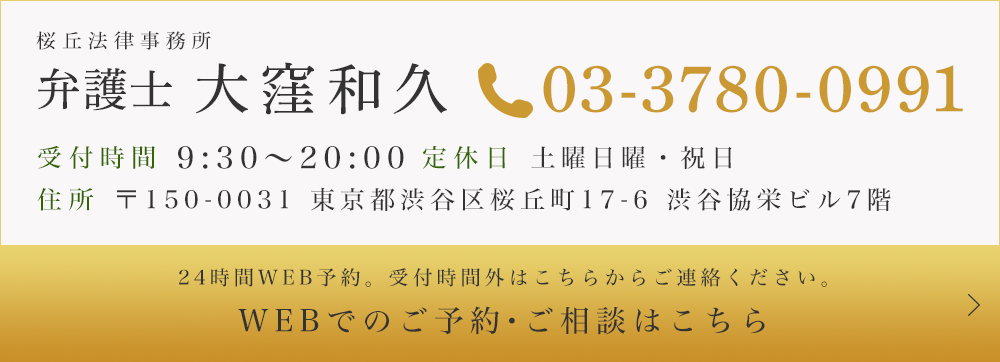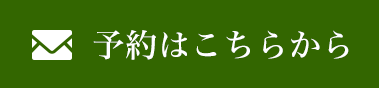新型コロナウイルスに便乗した詐欺事件が増加しています。朝日新聞の報道によれば、新型コロナウイルスに便乗した詐欺事件(未遂を含む)の被害は今年の3月上旬から5月17日までの間に、16都道府県で39件確認されており、被害額は約3550万円にのぼっているとのことです。
典型的な手口としては、特定定額給付金の手続の代行を行なうのでATMに手数料の振り込みを求めるであるとか、申請手続のために口座番号・暗証番号等個人情報を聞き出すなどです。そもそも特定定額給付金の申請は市町村から各世帯へ郵便で送付される申請書に記入し申請するか、「マイナポータル」によるオンライン申請のいずれかしかありません。また、役所の担当者が申請手続のために手数料の振り込みを求めるであるとか、個人情報を聞き出すということは絶対にありません。
上記のような電話やメールなどが来た場合、まず間違いなく詐欺ですので警察や消費生活センター等に相談することをお勧めいたします。また、仮に実際に手数料の振り込みを行なってしまったりした場合でも、早期の段階であれば振り込め詐欺救済法による銀行口座凍結等により、被害回復ができる場合もありますので、なるべく早めに相談にいくことをお勧めいたします。
また、給付金等の支給を受けられると騙った偽サイトにも注意が必要です。既に行政機関を騙った偽サイトが多数存在しているようです。また、サイトだけではなく偽の申請アプリ等が出現する可能性も否定できません。これらのサイト等はクレジットカード情報等を取得した上でそれを盗用するためにつくられているものです。給付金の支給のためにクレジットカード情報を入力する必要はありませんので、絶対に入力しないで下さい。仮に入力してしまった場合でも、早期であればカード会社によるチャージバックの手続などにより被害を防げる場合もありますので、なるべく早めに警察や消費生活センター等に相談することをお勧めいたします。
上記の手口以外にも、新型コロナウイルスに便乗した詐欺の発生することが懸念されています。不審な電話やメールがきたり、不審な人物が自宅に訪問してくるような場合には、その場で何かを決めるのではなく、家族、知人、あるいは消費生活センター等に相談しましょう。