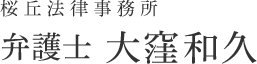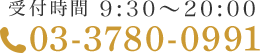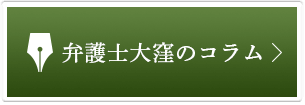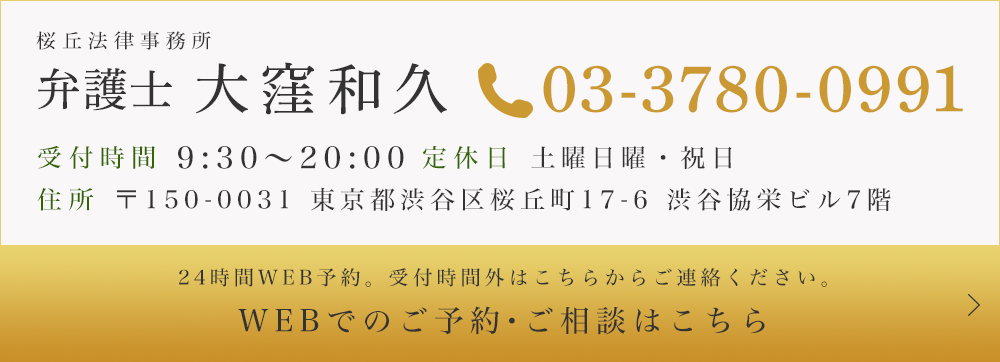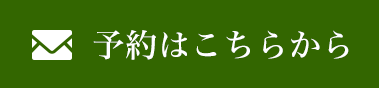現在、裁判手続のIT化が現実化しようとしています。
2017年6月9日に閣議決定された「未来投資戦略2017」のなかで、「迅速かつ効率的な裁判の実現を図るため、諸外国の状況も踏まえ、裁判における手続保障や情報セキュリティ面を含む総合的な観点から、関係機関等の協力を得て利用者目線で裁判に係る手続等のIT化を推進する方策について速やかに検討し、本年度中に結論を得る。」とされたことをうけて、2017年10月から8回にわたり裁判手続等のIT化検討会が開かれました。議論の内容等については公開されています。
同検討会の議論を経て、2018年3月30日に「裁判手続等のIT化に向けた取りまとめ」がなされました。同とりまとめでは、「3つのe」、すなわちe提出(オンラインによる提出)、e法廷(テレビ会議やウェブ会議の活用の大幅拡大)、e事件管理(電子情報での事件管理及び情報へのオンラインのアクセスを実現)を実現し、民事訴訟手続の全面的なIT化を目指すとしています。この取りまとめを受けて、日本弁護士連合会も「裁判手続等のIT化の取組を迅速かつ積極的に行っていく」として、単位会からの意見を取りまとめたうえ最高裁や法務省と協議を進めているところです。
一方、札幌弁護士会は先日裁判手続等のIT化について、司法過疎地の切り捨てのおそれがあること等から、拙速な検討を行うべきではないとの会としての意見書をだしました。またこの意見書の中では、「現在の技術水準の程度のテレビ会議・ウェブ会議のシステムを前提にする限り、裁判官と当事者・代理人が、直接会うことと同じレベルで接して感得することは到底期待し難い。あたかも現実に会って訴訟活動を遂行しているのと同様の効果が期待できるVR等の技術を活用するならばともかく、現状の技術水準でe法廷を推進することは、裁判の本質を不当に変質・劣化させかねず、妥当ではない」とも書かれており、事実上e法廷の導入を否定する見解を表明しています。
私はこれを読んで非常に驚きました。なぜなら、裁判手続等のIT化、特にe法廷の恩恵を一番受けるのは、まさに北海道の司法過疎地の住人であると思うからです。私は北海道の司法過疎地である旭川地方裁判所紋別支部管内で3年間、同裁判所名寄支部管内で5年間仕事をさせていただいておりましたが、支部管内住民にとって「裁判所が遠い」ということが司法アクセスへの大きな壁になっていることをこの目でみてきました。
たとえば紋別の住人が札幌地方裁判所で裁判を起こされた場合、裁判所まで片道4~5時間かけていく必要がでてきます。道外で訴訟を起こされた場合更に時間と費用を要します。逆に訴訟を起こしたくても、裁判管轄が地元の裁判所でなければ、訴訟を起こすこと自体躊躇せざるを得ないのが現状です。更に紋別や名寄という支部では裁判官が一人だけで合議が組めない事などの事情から扱える事件が限られているという問題もあります。
更に問題なのが独立簡裁です。旭川本庁から180キロ離れており、どの旭川の地裁支部(稚内・名寄・紋別)からも100キロ以上離れている中頓別簡易裁判所という独立簡裁があります。旭川から中頓別まで繋ぐ鉄道は廃止されており、移動手段は自動車しかありません。冬場になると地吹雪の中峠を越えなければならず、自家用車による移動すらままならないことも珍しくはありません。そして、この独立簡裁は、少し前までは電話会議システムすらなく、裁判所を利用しようとする当事者は裁判所への出頭を余儀なくされていました。
こうした場所的遠隔を乗り越えるための手段として、数多くの国で裁判手続でテレビ会議・ウェブ会議を活用しています。私は北海道にいる間、隣国ロシア(サハリン及びウラジオストク)に北海道弁護士会連合会の北方圏交流委員会のメンバーとして何回か訪れ、ロシアの裁判所や検察庁、法律事務所等を見学する機会をいただきました。そして訪問するたびに、裁判手続のIT化が進んでいっており、日本がこれから実現しようとする「3つのe」については既に実現しています。テレビ会議システムも各法廷に備わっており、例えばウラジオストクにある高等裁判所の事件についてサハリンの地方裁判所とつなぎ、当事者はサハリンの地方裁判所にいながら高裁の弁論を行うことが可能です。
私はこうしたシステムがあれば、場所的遠隔のため司法サービスを受けられない人、特に司法過疎地の人が救われると思いましたし、このようなシステムが一日も早く日本で導入されるべきだと考えています。そのため北海道の司法過疎地での上記問題およびこれを乗り越える手段となりうる隣国ロシアでの取り組みについて、各所で伝えてきました。5年前には日本裁判官ネットワークのシンポジウム「地域司法とIT裁判所」に参加して発表させていただく機会もありました。なおこのシンポジウムの内容は判例時報2212、2213号に掲載されていますので興味のある方は是非ご一読ください。
こうした司法過疎地での問題を抱え、かつ北方圏交流委員会の活動を通して隣国ロシアの司法状況についても日本で一番情報を有しているはずの北海道の弁護士が事実上e法廷の導入を拒否するというのは正直理解に苦しむというよりありません(なお札幌は地裁本庁のある札幌市には弁護士が集中していますが、公設事務所も設置されている司法過疎地が地裁管内にあり、司法過疎地の問題は他人事、というわけでは当然ありません)。
札幌弁護士会の意見書で裁判手続のIT化が司法過疎を促進するという理由は二つあげられています。一つ目の理由として、IT化されれば裁判所の機能が大規模庁に集約されてしまうおそれがあることをあげています。この点、北海道ではこれまで裁判所の機能が集約されてきたのは事実であり、例えば地裁支部では執行事件の取り扱いをやめるようになりました。この時に裁判所側は、執行事件は郵送で対応できるので集約しても弊害はないということを言ってましたので、IT化を理由として同じようなことを言われることを危惧しているのかもしれません。しかし裁判所機能集約とIT化は別の問題です。例えば執行事件が集約されるおそれがあるからといって、執行に関する書類の郵送での受理を取りやめるということにはならないでしょう。
札幌弁護士会の意見書では、「訴訟当事者・代理人も出頭を要しない手続が拡充されると、弁護士の東京への一極集中化をもたらしかねず、司法過疎地がますます広範囲になる」ということも理由としてあげています。しかしながら、e法廷はあくまでも裁判手続内の問題であり、利用者がどこの弁護士を選任するかという問題とは直接関連しません。むしろe法廷が実現すれば道内(とりわけ司法過疎地)の弁護士にとっても遠隔地の事件を受任しやすくなり、その結果地元の方にとってもメリットがあるのではないでしょうか。
私が危惧するのは、司法過疎地の現場を抱える北海道の弁護士が裁判手続のIT化、とりわけe法廷の導入に消極あるいは反対意見を出すことにより、司法過疎地の裁判所にはe法廷が導入されないという事態が生じないだろうかという点です。現に裁判所は中頓別簡易裁判所のように電話会議システムを長きにわたり簡裁に設置しなかったり、現行法上も設置することが認められているテレビ電話会議システムを地裁支部に設置しないということを行ってきました。これと同じことが裁判手続等のIT化でもまた繰り返され、「裁判手続のIT化から司法過疎地が切り捨てられる」ことのないよう願うばかりです。