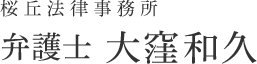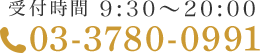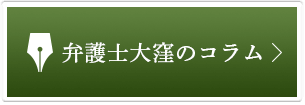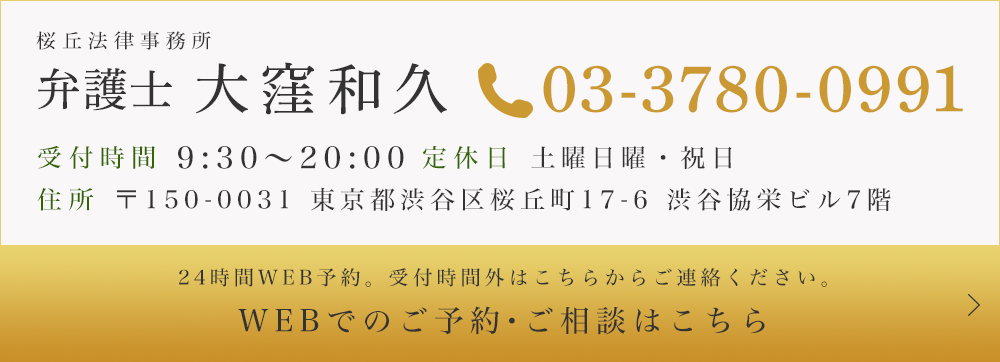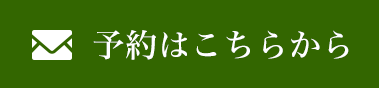読売新聞で「「社員が殺されても知らないぞ」匿名メールの情報開示認めず…最高裁が1・2審判断覆す」という記事が掲載されていました。
記事によると、「〈放火されて社員が殺されても知らないぞ〉2019年夏。東京都内の映像会社にこんな内容の匿名メールが繰り返し送りつけられた。36人が犠牲になった「京都アニメーション放火殺人事件」の直後だったこともあり、映像会社は責任を追及するため、送信者を特定することにした」「同社は、民事訴訟法の規定に着目。証拠の散逸などを防ぐために設けられた「証拠保全手続き」や、その証拠を提示させる規定を使い、ネット接続業者(プロバイダー)のNTTドコモを相手取り、送信者の氏名や住所などの開示を求める裁判を起こした」とのことです。
記事にも指摘がありますが、インターネット上での誹謗中傷の投稿者の発信者情報開示に用いられるプロバイダ責任制限法は、不特定多数に向けられた投稿のみを対象としており、メールやダイレクトメッセージといった「1対1」のメッセージは対象外とされています(この点日弁連からはプロバイダ責任制限法の改正にあたり「実効的な発信者情報開示請求のための法改正等を求める意見書」内において「1対1」のメッセージの送信者情報も開示の対象に含めるべきとの意見がでておりますが、改正法でもこの意見は入れられませんでした)。そこで被害に遭った映像会社は、訴えの提起前における証拠保全として,送信者の氏名・住所が記録された記録媒体等につき検証の申出をするとともにNTTドコモに対する検証物提示命令の申立てを行なったのです。
この点原決定(東京高裁)は、「本件メールが明白な脅迫的表現を含むものであること、本件メールの送信者情報は本件送信者に対して損害賠償責任を追及するために不可欠なものであること、本件記録媒体等の開示により本件送信者の受ける不利益や抗告人に与える影響等の諸事情を比較衡量すると、本件記録媒体等に記録され、又は記載された送信者情報は保護に値する秘密に当たらず、抗告人は、本件記録媒体等を検証の目的として提示する義務を負う」との判断を行い、申立てを認めました。
しかしながら、最高裁判所第1小法廷の決定(令和3年3月18日 令和2年(許)第10号)では、次のような理由付で原決定を破棄して申立を却下しました(なおこの決定は先日までは最高裁ホームページに掲載されていましたが現在は掲載されていないようです。裁判所時報1764号3頁には掲載はなされています。)
「(1) 民訴法197条1項2号は、医師、弁護士、宗教等の職(以下、同号に列挙されている職を「法定専門職」という。)にある者又は法定専門職にあった者(以下、併せて「法定専門職従事者等」という。)が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合には、証言を拒むことができると規定する。これは、法定専門職にある者が、その職務上、依頼者等の秘密を取り扱うものであり、その秘密を保護するために法定専門職従事者等に法令上の守秘義務が課されていることに鑑みて、法定専門職従事者等に証言拒絶権を与えたものと解される。
電気通信事業法4条1項は、「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。」と規定し、同条2項は、「電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。」と規定する。これらは、電気通信事業に従事する者が、その職務上、電気通信の利用者の通信に関する秘密を取り扱うものであり、その秘密を保護するために電気通信事業に従事する者及びその職を退いた者(以下、併せて「電気通信事業従事者等」という。)に守秘義務を課したものと解される。
そうすると、電気通信事業従事者等が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合に証言を拒むことができるようにする必要があることは、法定専門職従事者等の場合と異なるものではない。
したがって、電気通信事業従事者等は、民訴法197条1項2号の類推適用により、職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて証言を拒むことができると解するのが相当である。
(2) 民訴法197条1項2号所定の「黙秘すべきもの」とは、一般に知られていない事実のうち、法定専門職従事者等に職務の遂行を依頼した者が、これを秘匿することについて、単に主観的利益だけではなく、客観的にみて保護に値するような利益を有するものをいうと解するのが相当である(最高裁平成16年(許)第14号同年11月26日第二小法廷決定・民集58巻8号2393頁参照)。
電気通信事業法4条1項が通信の秘密を保護する趣旨は、通信が社会生活にとって必要不可欠な意思伝達手段であることから、通信の秘密を保護することによって、表現の自由の保障を実効的なものとするとともに、プライバシーを保護することにあるものと解される。電気通信の利用者は、電気通信事業においてこのような通信の秘密が保護されているという信頼の下に通信を行っており、この信頼は社会的に保護の必要性の高いものということができる。そして、送信者情報は、通信の内容そのものではないが、通信の秘密に含まれるものであるから、その開示によって電気通信の利用者の信頼を害するおそれが強いというべきである。そうである以上、電気通信の送信者は、当該通信の内容にかかわらず、送信者情報を秘匿することについて、単に主観的利益だけではなく、客観的にみて保護に値するような利益を有するものと解される。
このことは、送信者情報について電気通信事業従事者等が証人として尋問を受ける場合と、送信者情報が記載され、又は記録された文書又は準文書について電気通信事業者に対する検証物提示命令の申立てがされる場合とで異なるものではないと解するのが相当である。
以上によれば、電気通信事業者は、その管理する電気通信設備を用いて送信された通信の送信者情報で黙秘の義務が免除されていないものが記載され、又は記録された文書又は準文書について、当該通信の内容にかかわらず、検証の目的として提示する義務を負わないと解するのが相当である。」
上記の通り、最高裁の判断は、送信者本人が開示に同意するような場合を除けば一切送信者情報の開示を認めないというものです。この点、本件が現に京アニ事件を模倣した極めて悪質な内容の脅迫を受けている被害者による申立であることを考えると、利益考慮の点では原決定のように送信者情報については開示を認めるのが妥当ではないかと私は考えますが、そのような利益考慮を前提とした判断を最高裁は行ないませんでした。そして最高裁が現行法のもとでは開示を認められないと判示してしまった以上、今後民事手続において匿名者のメールやダイレクトメッセージの送信者情報の開示を求めることは不可能になりました。
勿論、刑事手続上では捜査機関がプロバイダに捜査関係事項照会を行なったり、裁判所の令状を取って捜索差押を行なう場合には、プロバイダがこれに応じて送信者情報の開示に応じることはあります。ただ捜査を行なうかどうかは捜査機関の判断に委ねられており、匿名者の脅迫や詐欺被害について捜査機関が捜査に着手しない場合には、被害救済の手段は一切閉ざされてしまうことになります。脅迫や詐欺の加害者が匿名であり、メールやダイレクトメッセージ、LINEしか手がかりがないような場合には事実上泣き寝入りすることになるおそれが高いです。
私は、脅迫や詐欺の被害者に迅速に民事的な被害回復を実現させるため、立法により送信者情報の開示を認めるべきであると考えます。立法に当たっては当然憲法上の権利である通信の秘密の保護をどのように図るかは慎重に検討されるべきですが、少なくとも犯罪被害回復の為に通信の内容そのものではない送信者情報については開示の手段を設けるべきでしょう。