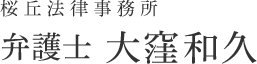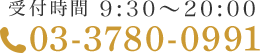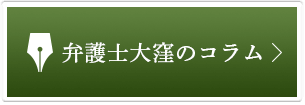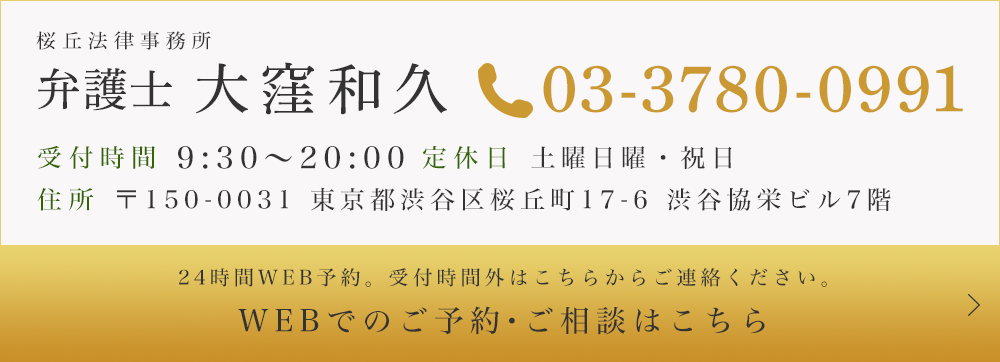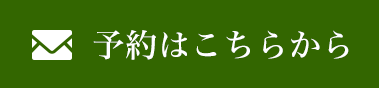証拠開示のデジタル化を実現する会(URL https://www.change-discovery.org/)において、今月20日まで、刑事訴訟における検察の証拠開示について、紙でコピーさせるのをやめて電子データで渡すことを求めることについて賛同の署名を募集しております。私も署名いたしました。
刑事訴訟において、検察官から弁護人は証拠開示を受けることになりますが、この場合原則として弁護側が検察庁に訪れ、証拠を一枚一枚紙でコピーをしなければなりません。このコピー代が馬鹿にならず、例えば私が現在弁護人になっている事件(公訴事実に争い有り)でも、コピー代が50万円以上に達しています。コロナ渦の現在においても、紙のコピーを取りに行ったり、業者がコピーした大量の紙のコピーを引き取りに行かねばなりません。遠隔地の検察庁であれば、わざわざ紙のコピーを確保するために、弁護人側がコピー代だけではなく旅費等も負担した上証拠開示を受けることも珍しくはありません。
民事訴訟では、IT化が徐々にでは有りますが日本でも進みつつあり、書証についてもデジタルデータでの提出が議論されていますが、刑事裁判においては明治時代と変わらない紙ベースの裁判が続けられており、大量の書面が用いられています。IT化の議論も全くなされていませんし、証拠開示についても検察庁は証拠をPDFファイルなどの電子データで渡すことを拒否しています。ただこれは極めて非効率ですし、個人がコピー代等大きな負担を強いられることになってしまいます。
証拠開示のデジタル化を実現する会のサイトでは、海外の事例も紹介されています。例えば、隣国韓国では、民事訴訟だけではなく刑事訴訟のデジタル化も進めているということです。韓国は民事訴訟のIT化については日本の10年先を進んでいますが、刑事訴訟でも先を行かれることになりそうです。また、アメリカNY市では、クラウドストレージでの証拠開示が行なわれているようです。
時代遅れの司法によって個人が不利益を受けるという実態を少しでも改善していく必要があります。悪しき実態を改善させるため、刑事裁判の証拠開示はデジタル化されるべきと考えます。賛同頂ける方は証拠開示のデジタル化を実現する会の賛同の署名をお願い致します。